該当しそうな、免除制度を確認しよう
年金は、20歳から60歳に達するまで保険料を払わなければなりません。
しかし、そんなことを言われても、人生色々あります…
毎月、毎月、17,510円(R7年度保険料額)を、40年間払わなければ、と考えると、
ゾッとしてしまう人もいるかも知れません。
しかし、今から、そんな先の話を考えると憂鬱になってしまうので、
「ケ.セラセラ」
「まあ、なるようになるさ!」
と、開き直って見ませんか?
とは言え、危機管理は必要です。
そんな時のために、こんな時には、こんな方法がある!ということご紹介いたします。
いざ、そうなったら、「こんな手があった!」と思い出して見て下さい。
それでは、始めます。

支払いができない時のための「免除」という制度
以前、年金は、厚生年金と、国民年金があるとお伝えしました。
そう、厚生年金については
厚生年金の適用事業所等に使用される70歳未満の人で、適用除外に該当しなければ、
給料から、健康保険料、厚生年金保険料等ひかれてしまうので、何も考えなくて大丈夫です。
私も、44年間、振り込まれる額にしか、興味がありませんでした…
会社勤めは何かと大変ですが、年金については、とても楽でお得です。
しかし、会社の年金に入れない方もいます
退職して無職の方、
自営業の方、
学生の方など
は、20歳の誕生月から60歳に達するまで、国民年金の保険料を支払わなければいけません。
しかし、なんらかの事情で、支払いができない時のための「免除」という制度が
大きく分けて5つあります。
- 法定免除
- 全額免除
- 一部免除(3/4、半額、1/4)
- 学生等の保険料納付特例
- 納付猶予
です。
また、これらの保険料免除と趣旨や性格が異なるもので、
「産前産後期間の保険料の免除」というものもあります。
「学生等の保険料納付特例」について
今回は、「学生等の保険料納付特例」 について見ていきたいと思います。
何度もお話するように、年金は、制度がどんどん変わっていきます。
それって、国が年金を減らすためにやってるのでは?と思う方がいるようですが、
たしかに 年金制度が、賦課方式のため、
(現役世代が支払った保険料を仕送りのように高齢者の年金給付に当て、それに、税金も足している。)
少子高齢化の日本では昔の方々より、かなり年金額が減ってきています。
しかし、今年生まれた子が100歳になるまで、年金制度を続けるための制度変更です。
昭和36年4月から、保険料拠出制(保険料を払って、保障を受ける制度)の国民年金がスタートしました。
専業主婦、国会議員、地方議会議員などは、昭和61年3月まで、
学生は平成3年3月まで、任意加入できる制度となっていました。
(加入したい人は申し出て、お金を払って下さいというもの)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)とは、
任意…となると、なかなか自分で手続をして、お金を毎月払って、と、いう方は少なかったようです。
平成3年3月以前に学生だった方(昭和45年以前生まれの方)は、任意加入しなかった期間は、合算対象期間(いわゆるカラ期間)となり、任意加入した方は、納付済期間となります。
受給資格期間の計算対象にはなりますが、老齢基礎年金の年金額の計算対象とはならないため、「カラ期間」ともいわれているものです。
平成3年3月以降、学生も強制適用
平成3年3月以降、学生も強制適用となっています。
しかし、毎月の保険料を払うのはなかなか難しい時は、
「学生等の保険料納付特例」
と、いうものがあります。
これは、学生であり、収入が基準以下なら、年齢制限(何浪しても大丈夫です。)がなく、申請した場合、指定期間、保険料を納付しなくてもいい、という制度です。
ただし、対象となる、学校(高校、大学等)や、所得等については、ご自分が、該当するか?について、住所地の市区役所・町役場の国民年金窓口、年金事務所での確認が必要です。
この手続きをした場合、障害基礎年金や、遺族基礎年金については、支給要件を満たせば、満額の年金が支給されます。
老齢基礎年金については、受給資格期間には算入されますが(年金受給要件の10年)年金額の計算については、追納(10年以内)されない限り、算定基礎とされません。
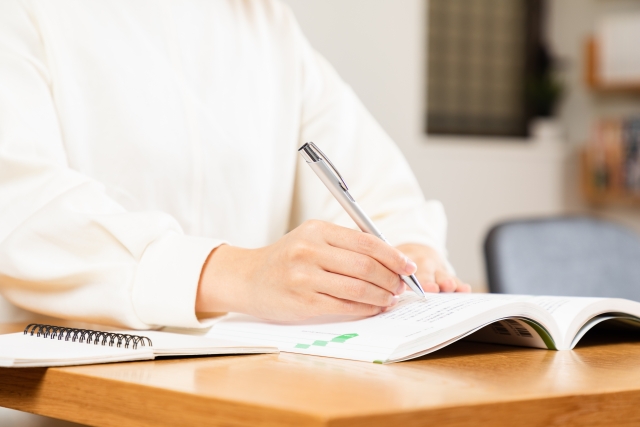
「学生等の保険料納付特例」 詳細
「所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数✕38万円+社会保険料控除等
学生とは、
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校
『学生納付特例対象校一覧』から確認できます。」
と、(日本年金機構2025.4.1 国民年金保険料の学生納付特例制度)に書かれています。
詳しくは、ご確認下さい。
学生の遺族基礎年金・障害基礎年金
遺族基礎年金は、前回までのシリーズでお話した通り、「子のある配偶者」にしか支給されないため、年齢的には、該当者は少ないとは思いますが、障害基礎年金は、可能性がないとは言えません。
障害基礎年金は、保険料納付要件というものがあります。
それは、
「初診日前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるものについては、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あること。」
とあります。(法律の文は難しい…)
つまり…、
今まで手続きをせず未納だったけど、病院で診察をしたら、今後障害者になりそうなので
慌てて今日手続きをしよう! とか、
遡って保険料を支払おう!
と思っても、間に合わない! ってことです。
なにせ、確認するのは、「初診日前日において…」なので…。
年金は、保険です。
リスクに備えてしっかり手続きしましょう。
おわりに
桜前線が、どんどん北上しています。
前職の防衛省では、3.4月に多くの方々が全国異動します。
北へ異動する人は、その年2回桜を見られたり、南に異動する人は、その年1度も桜を見れなかった。などの話をよく聴きました。
今年は、3月に東京で5日も雪が降ったり、3月平均気温約5.4℃の新潟県の高田で、真夏日になったり、桜も、それにまつわるイベントを企画する方々も大変ですね。

いよいよ新年度になり、いろいろな制度も改正されました。
次回も、色々な免除についてみていきたいと思います。
それでは









