今、検討されていること
遺族年金はなくなるの?シリーズ、最終回です。
3月ということもあり、テレビのドラマも最終回とよく目にする季節になりました。
ぽかぽかとして、庭の梅や桃の花が咲いて、春を感じたと思ったら、雪が降ったり。
季節も、人生も、「山あり谷あり」何が起きるかわかりません。
そんな、人生のリスクに備えるのが、保険です。
保険というと、街によくある、保険相談窓口などの、民間保険を思い浮かべる方が多いと思います。
死亡、
医療、
介護 など。
しかし、厚生年金も、保険です。(国民年金は?)
保険は、保険料を払った人に補償する制度です。
厚生年金は、給料から保険料を払い、事故があったときに補償してもらいます。
しかし、国民年金は、第3号被保険者とか、20歳前障害とか、保険料を払ってなくても補償される制度があるため、
国民年金は、保険が入らない 「国民年金法」、
厚生年金は、保険が入った 「厚生年金保険法」
で色々な制度が決められています。
障害、遺族、老齢。(老齢?)
そう、歳を取ることも、リスクです。老後には、経済面、健康面、介護面などさまざまなリスクがあります。
そのなかで、前回までの3回で、現在の遺族年金のしくみを見て来ました。
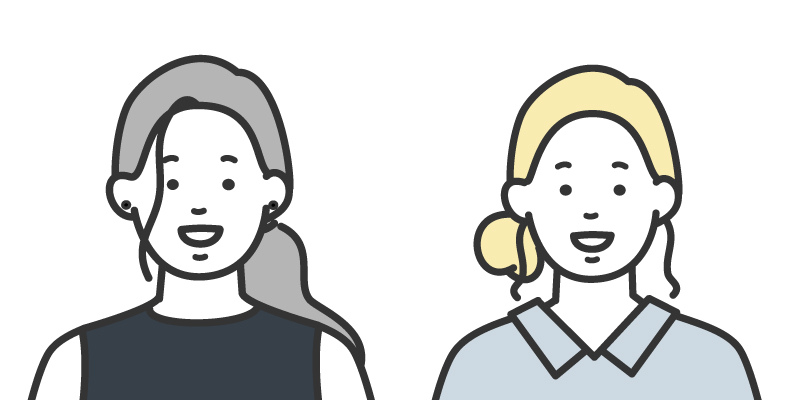
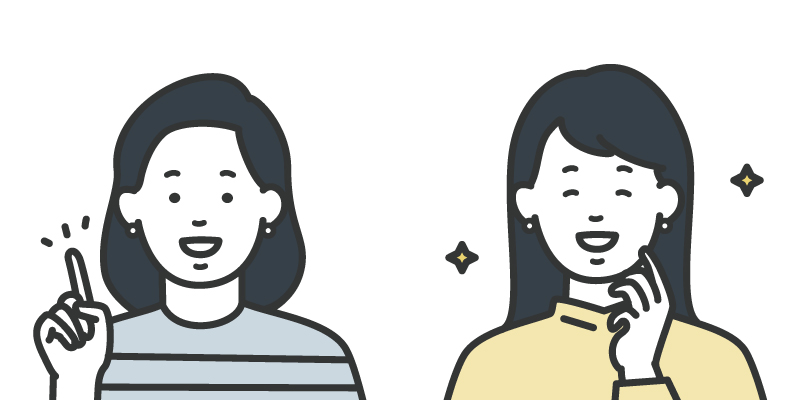
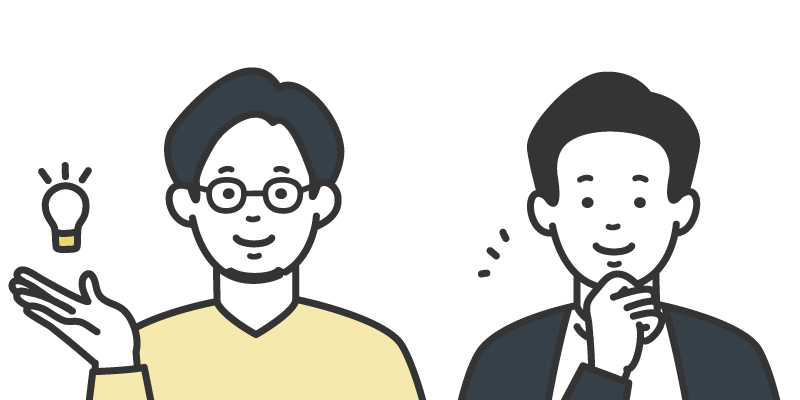
ネットなどで話題になった遺族年金ですが、令和6年7月に、厚生労働省で遺族年金制度等の見直しについて話し合われ、その後、令和6年12月に、7月の案についての見直しについて話し合われました。
もちろんこれは、まだ案なので変更されるかもしれませんが、その時の案について簡単に見ていきましょう。
そもそもの、見直しが必要とされる問題は、
遺族厚生年金の制度に男女差があり、子のない男性には給付されないケースもある。
ところです。
これまで見てきた通り、極端な話では
子のない女性は31歳で夫をなくすと、遺族厚生年金が一生もらえます。
しかし、
子のない男性は、55歳未満で妻を亡くしても、年金はもらえません。
その上、女性は40歳以上で夫をなくすと、中高齢寡婦加算が60万円位加算されます。
そこで今検討されている内容は、20年かけて段階的に
- 新たに子のない男性にも遺族厚生年金を支給する。
- 年金額を増額する。(有期給付加算+死亡分割)
- 配慮が必要な方は、5年目以降も継続受給を可能にする。(所得、障害等)
- 収入にかかわらず受給可能にする。
- 中高齢寡婦加算を廃止
- 親と同居する子に対する遺族基礎年金の支給停止規定の見直し
が、検討されています。
❶ 新たに子のない男性にも遺族厚生年金を支給する。
基本、現行の30歳未満の妻の5年有期年金を、60歳未満の全員に当てはめるイメージです。
子どもがいる場合は、現行どおり、遺族基礎年金を子どもが18歳年度末までもらい、
遺族基礎年金終了から5年間は、年金をもらい続けられます。
また、60歳以上は、無期年金になります。
❷ 年金額を増額する。(有期給付加算+死亡分割)
現在よりは、金額の増額(有期給付加算)が望めそうです。
また、死別を離婚と同じとみなし、離婚分割の制度と同じように、65歳からの年金に、配偶者分の標準報酬を加算することも考えられています。
❸ 配慮が必要な方は、5年目以降も継続受給を可能にする。(所得、障害等)
5年間というのは、生活を再建する時間と考えられていますが、障害や、低所得等により、5年で生活再建に至ってない人へは、給付の継続もあるようです。
❹ 収入にかかわらず受給可能にする。
現在、所得制限が、850万円となっているところの、所得制限をなくすことにより、一定以上の所得があっても、5年間は、遺族厚生年金をもらえることになりそうです。
❺ 中高齢寡婦加算を廃止
女性だけの制度は、段階的に廃止します。
❻ 親と同居する子に対する遺族基礎年金の支給停止規定の見直し
これについては、少し複雑になりますので、次回のテーマといたします。
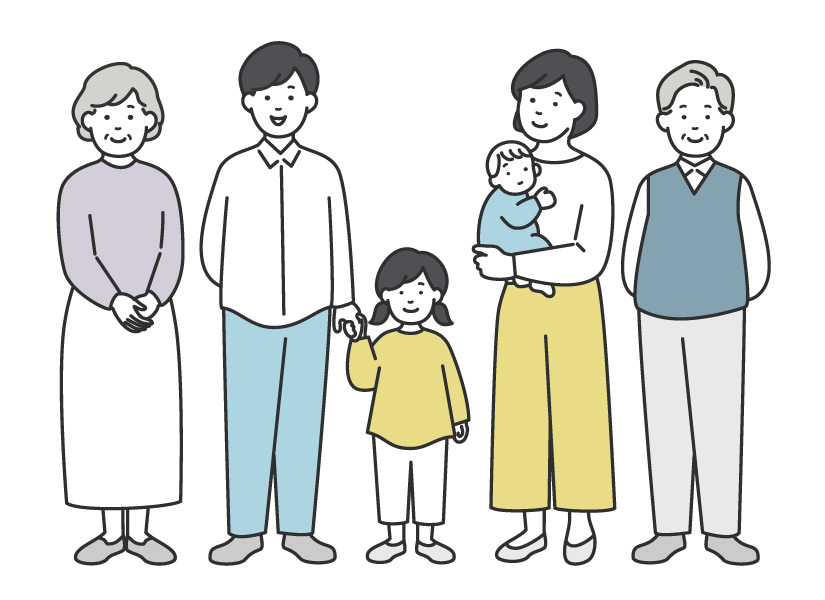
これからはどうなるのか?
現行の制度が考えられてから、3,40年でしょうか?
すっかり、さまざまな制度や、人々の考え方も進化して、昭和の当たり前を話すと、
「不適切!」などといわれてしまう時代になってきました。
しかし、その時代に生きてきた人は、その時代でのより良い制度を目指して頑張った結果と思っています。
年金は、複雑でわかりづらいというお話をさせていただきました。
今回の見直しもそうですが、これは20年計画となっています。5年毎に、少しずつ変えていきます。
その上、この見直しの前に年金をもらいだしている人は、その時の制度が続いていくため、色々な制度の人たちが混在して、ますますわかりづらくなっていきます。
しかし、それは、その時その時の時代に合わせて見直している証拠でもあると私は思います。 難しいことは考えずに、自分はどうなるかだけ、考えて見ませんか?









