まずは、遺族年金を知ろう!(中高齢の寡婦加算)
結論 遺族年金は、なくなりません。
結論 遺族年金は、なくなりません。
時代に合わせて、「見直し」 が行われるという話です。
その見直しを見る前に、現行の遺族年金について見ていきます。
前回の1回目で、公的年金は2種類あり、それぞれ老齢、障害、遺族年金がある、
そして遺族年金とは、
年金を掛けている、または掛けていた人(被保険者、被保険者であった人)が、亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族の所得を保障するための年金です。
というお話をしました。
そして、この遺族年金は、とても複雑なしくみであるため、
- 20代女性(前回、有期年金について)
- 30代(アラフォー)女性
- 50代男性
を例に見ていくことにしました。
❷【30代女性】の場合
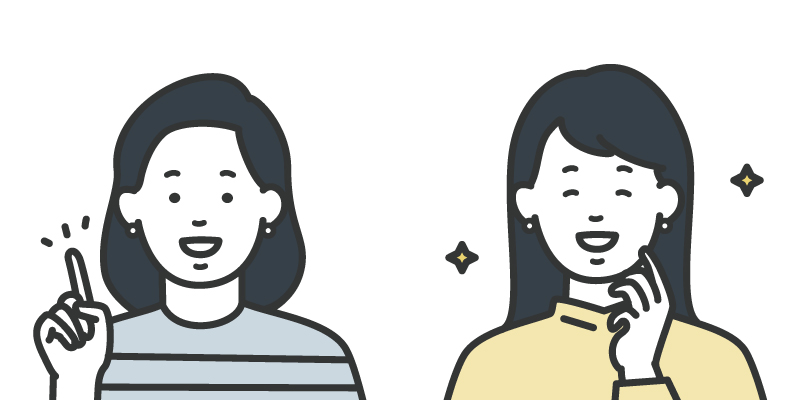
そして今回2回目は、❷30代(アラフォー)女性です。
いずれも、2024年度の金額で、諸条件を満たしているとします
(生計同じ、遺族の収入850万未満等)
それでは、いよいよ
1、 アラフォー女性が3人
A子(39歳)、B子(39歳)、C子(40歳)
ともに、会社員の夫がいましたが、亡くなってしまいました。
2 A子には、12歳の子がいます。
B子、C子には、子どもがいません。
それでは、もらえる年金は? How much?
アラフォー女性が夫をなくした場合 どのような年金を、
いつから、いつまでもらえるのでしょうか?
遺族基礎年金(国民年金)
前回、お話したとおり、18歳年度末までの子のない配偶者(B子、C子)は
遺族基礎年金をもらえません。
もらえるのはA子だけです。
金額は、 816,000円+234,800円=1,050,800円(年額)
この金額は、国民年金を40年掛けた人がもらえる老齢基礎年金満額の 816,000円と同額に、子ども1人分の234,800円を、夫が亡くなった翌月から、子どもが18歳年度末になるまでの約8年間受給出来ます。
(手続きが必要です)
1,050,800円✕8年=8,406,400円
次に、夫の加入していた、遺族厚生年金についてです。
遺族厚生年金(厚生年金)
3人とも、夫が65歳から支給される予定だった
「老齢厚生年金 報酬比例部分」 の3/4の金額がもらえます。
報酬比例部分
これは、どれだけの金額を、何年払ったかで決まるものです。
払った期間が短い場合、300月みなしや、最低保障が該当する場合があります。
遺族厚生年金については、3人とも65歳までもらえます。
しかし!! A子とC子には、B子がもらえない
「中高齢の寡婦加算(612,000円/年額)」
という厚生年金をもらうことができます。
なぜ!?
中高齢の寡婦加算とは、遺族基礎年金を支給されない一定の 妻 に支給されます。
遺族厚生年金(被保険者期間240月以上等条件あり)の受給者である
妻 (配偶者ではない)であって、
妻 が、65歳未満であり、1、2に該当するときに加算されます。
- 夫の死亡当時、40歳以上65歳未満である (C子該当)
- 40歳に達した当時、夫の死亡の当時その夫により生計を維持し、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態にあり、 かつ、現に婚姻をしていない子と生計を同じくしていたこと
(A子該当ですが、遺族基礎年金の支給中は、支給されません)
と、いうことで、A子は、47歳で遺族基礎年金は終了し、その後から、
C子は、はじめから、「中高齢の寡婦加算」(厚生年金)をもらうことができます。
612,000円/年額✕25年(40歳から65歳前まで)=15,300,000(C子)
そして、65歳からは、3人とも、
自分の年金と、夫の遺族厚生年金とを、選択してもらうこととなります。
| 39歳 | 40歳 | 47歳 | 65歳まで | 65歳から | |
|---|---|---|---|---|---|
| A子 | 遺基1,050,800子18歳末まで(約8,406,400円) | 中高齢612,000 (約11,016,000円) | 自分の老齢基礎年金 + 夫の遺族厚生年 or 自分の老齢厚生年金 (特例あり) | ||
| 遺厚 比例3/4 | |||||
| B子 | 遺基 なし | ||||
| 遺厚 比例3/4 | |||||
| C子 | 遺基なし、 しかし中高齢612,000円あり (約15,300,000円) | ||||
| 遺厚 比例3/4 | |||||
しかし、今回の「中高齢の寡婦加算」も、前回の「有期年金」も、
男性には該当しません。

ということで、男女平等が叫ばれる中、見直しが必要では?との話が出てきています。
それでは、次回は最後の50代男性の例で見ていきます。
それでは…








