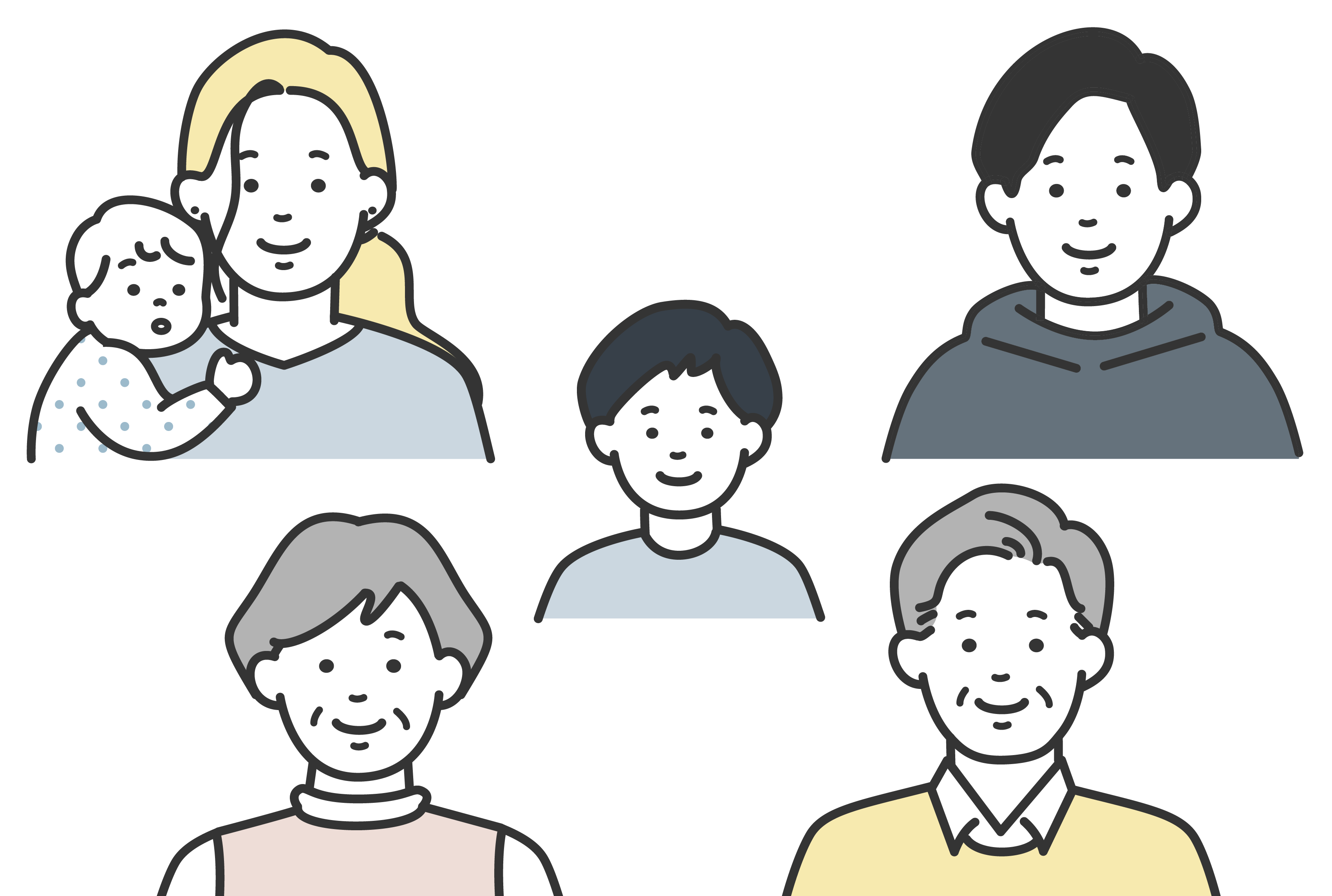親と同居する子に対する遺族年金見直し(案)
前回までの4回で、遺族年金の改正案について見てきました。
その内容は、下記の内容6項目を、20年掛けて段階的に改正しようと話合われていると、お伝えしてきました。
- 新たに子のない男性にも遺族厚生年金を支給する。
- 年金額を増額する。(有期給付加算+死亡分割)
- 配慮が必要な方は、5年目以降も継続受給を可能にする。(所得、障害等)
- 収入にかかわらず受給可能にする。
- 中高齢寡婦加算を廃止
- 親と同居する子に対する遺族基礎年金の支給停止規定の見直し
前回、1から5までについては、内容を簡単に説明させていただきました。
【遺族年金はなくなるの?シリーズはこちらからスタート!】
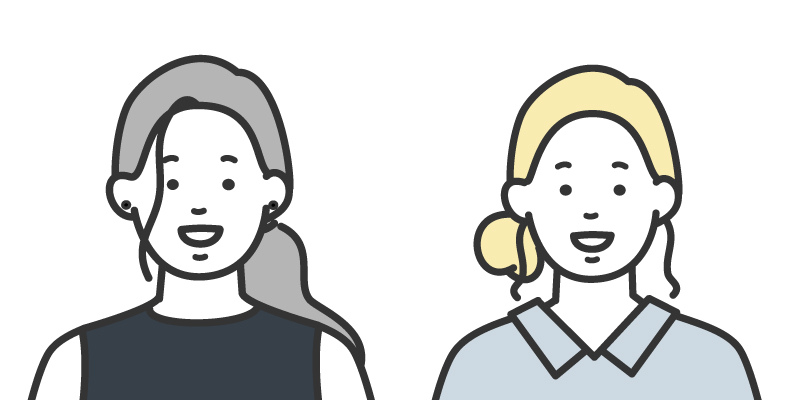
今回は、6について、少し見ていきたいと思います。
まずは、基本のお話です。
遺族年金はなくなるの?シリーズで、
遺族基礎年金は、国民年金の、諸条件に該当する、被保険者又は被保険者であったものが死亡した時、
そのものによって生計を維持していた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。
「子」とは、18歳に達する日以後の3月31日までにある(概ね高校3年生)か、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしてない人をいいます。
実は、年金では、配偶者は事実婚でも認められますが、子どもは、「法律上の子」しか認められません。
遺族基礎年金は、「子のある配偶者」の場合、配偶者に給付され、「子」は支給停止になります。
「配偶者」は、養育する「子」が、いなくなったり、再婚したり、所得が850万円を超えていると「配偶者」への年金は支給されなくなります。
「子」は 親等と生計を同じくすると、年金は支給されないしくみになっています。
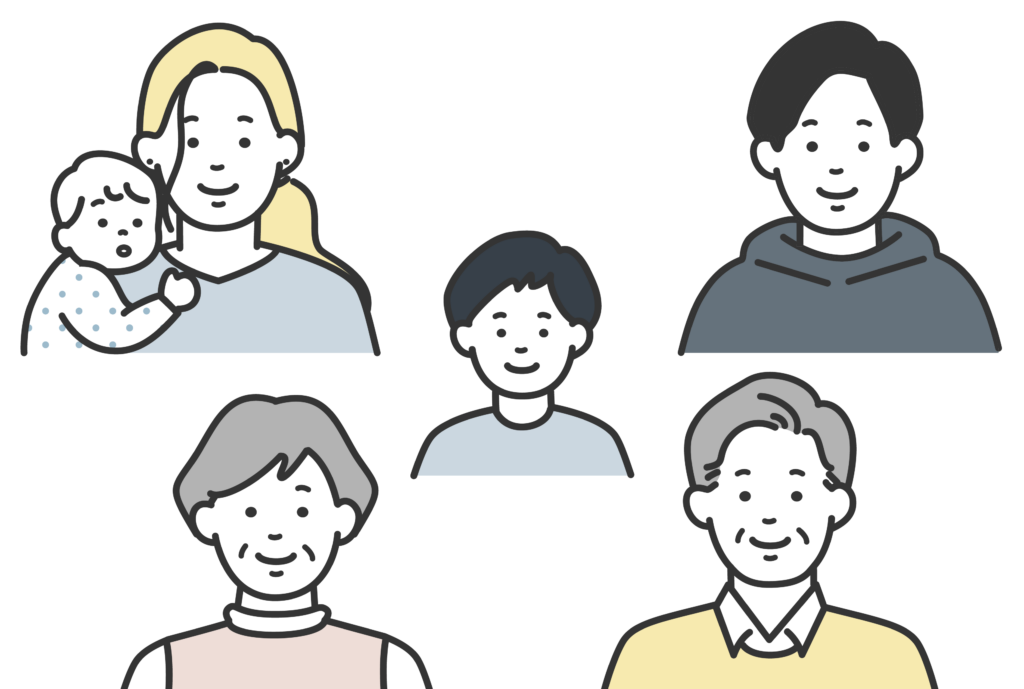
遺族基礎年金 支給停止の例
ということで、支給停止の例として、
1 父母が離婚し、父の元で暮らしていたが、父が死亡したため、母に引き取られた場合
母は、配偶者ではないため、遺族基礎年金はもらえない。
子は、母と生計を同じくしているため、遺族基礎年金は支給停止
2 残された配偶者が、再婚した場合
配偶者は、再婚により、失権
子は、父母と生計を同じくしているため、遺族基礎年金は支給停止
3 子が祖父母等(直系血族又は姻族)に引き取られ、養子縁組した場合
祖父母等に、遺族基礎年金は発生しない
子は、父母等と生計を同じくしているため、遺族基礎年金は支給停止
4 残された配偶者が、収入850万円以上の場合
配偶者は、遺族基礎年金に該当せず
子は、親と生計を同じくしているため遺族基礎年金は支給停止
厚生労働省の資料によりますと、
離婚増加等の、子を取り巻く家庭環境の変化を踏まえ、子の置かれている状況による
遺族基礎年金の支給停止の不均衡を見直し、自らの選択によらない事情で、子が置かれている状況による、遺族基礎年金の支給停止がされることがないよう、規定を見直す。
とあります。
幼い子どもは、一人では生きていけません。
その子を、育ててくれる人が、収入850万円未満の、法律上の「親」でなければ、
遺族基礎年金がうけとれないなんて・・・・
一刻も早く、見直しをしていただきたい内容だと思います。
年金は、このような問題ついて、色々見直しがされています。
今はだめでも、何年後かは受給できるようになったりもします。
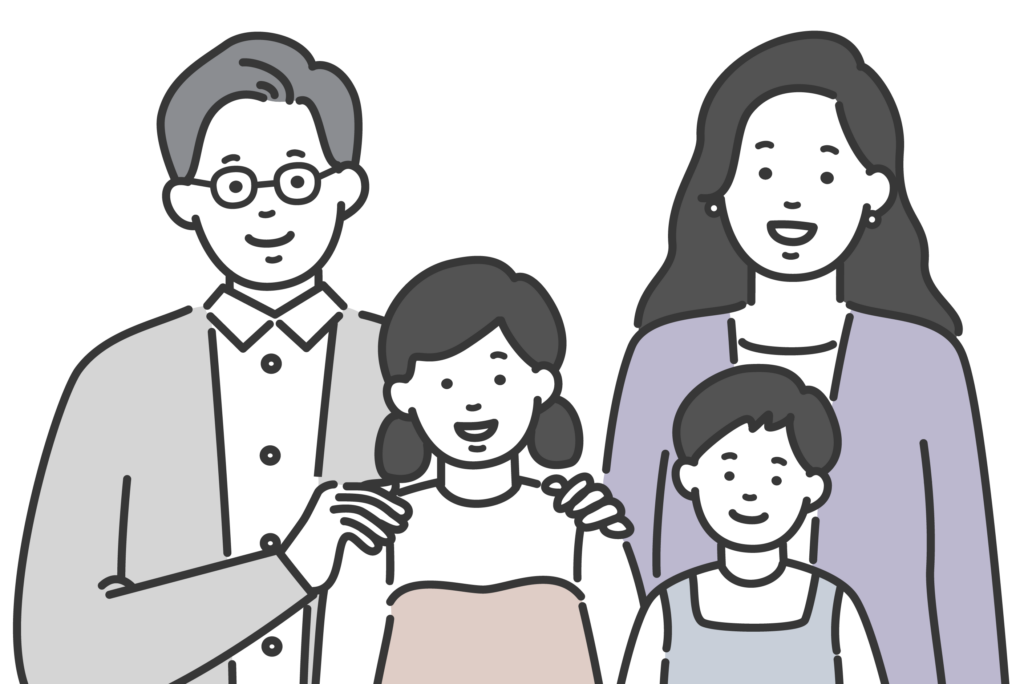
次回からは別シリーズ!
次回からは、掛金を収める余裕がない時の、免除や未納についてみていきたいとおもいます。
いよいよ、春
実家に向かう途中の荒川の河原は、一面、菜の花で黄色く染まっていました。
そろそろ、桜前線も、やってきそうですね。

色々、忙しいと思いますが、花を見て、「きれい!」と思える、そんな穏やかな気持ちになれる時間を、少しでも持てるといいですね。
それでは、また。