まずは、遺族年金を知ろう!(若年停止)
結論 遺族年金は、なくなりません。
時代に合わせて、「見直し」 が行われるという話です
その見直しを見る前に、現行の遺族年金について見ていきます。
前回までの2回で、公的年金は2種類あり、それぞれ老齢、障害、遺族年金がある、
そして遺族年金とは、
年金を掛けている、または掛けていた人(被保険者、被保険者であった人)が、亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族の所得を保障するための年金です。
というお話をしました。
そして、この遺族年金は、とても複雑なしくみであるため、
を例に見ていくことにしました。
❸【50代男性】の場合
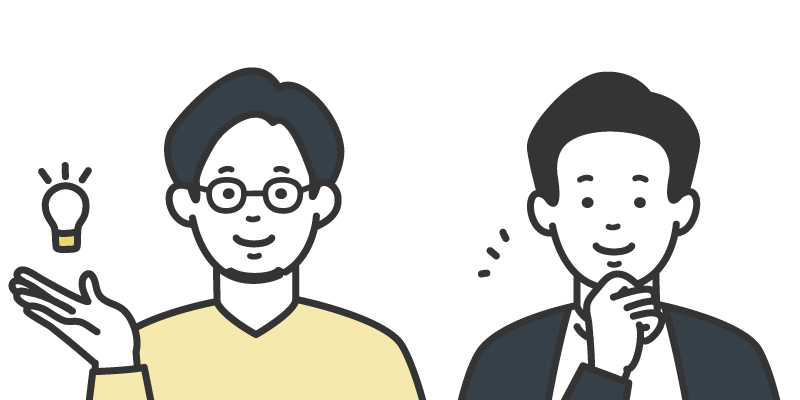
そして今回3回目は、❸50代男性です。
いずれも、2024年度での諸条件を満たしているとします
それでは、いよいよ見てみましょう。
1、 50代男性が3人
A男(54歳)、B男(55歳)、C男(55歳) 年収900万円 60歳定年
子どもはなく、ともに、年上の老齢厚生年金受給中の妻(65歳)が亡くなってしまいました。
2、3人の妻たちは全員、過去に会社員として10年間厚生年金を掛けていました。
A男とB男の妻は、結婚後、国民年金3号(※)期間が、15年あります。
※国民年金 第3号被保険者制度は廃止されるの!?(R7.1.10掲載)参照
しかし、C男の妻は、再婚前、国民年金は払っていなかったため厚生年金10年以外の期間はありません。
彼ら3人は、遺族年金はもらえるのでしょうか?
遺族基礎年金(国民年金)
シリーズ1回でお話したとおり、
18歳年度末までの子のない配偶者は遺族基礎年金をもらえないため、
3人とも遺族基礎年金はありません。
次に、妻の加入していた、厚生年金についてです。
遺族厚生年金(厚生年金)
1 遺族厚生年金の支給要件(対象者)について
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者(加入中)又は被保険者であったものが、いくつかの条件に該当するときに、その遺族に支給されます。
その中に
- 被保険者が死亡したとき(第1回、2回で登場した夫の場合)
- 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付期間と保険料免除とを合算した期間が25年以上であるものに限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
と、あります。
つまり、年金受給中又は、65歳になって請求すればもらえる資格がある人ヘの条件です。
そのため、C男は、妻の納付期間が10年のため遺族厚生年金はもらえません。
平成29年7月までは、受給資格期間が25年ないと老齢年金はもらえませんでした。
現在は10年あれば老齢年金をもらうことができますが、遺族年金については、25年の条件が残っています。
次に、遺族の範囲です。
2 遺族の範囲
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持した者とする。ただし、妻以外の者にあっては、次の(1)又は(2)に該当した者に限るものとする。
- 夫(配偶者ではない)、父母、祖父母については、55歳以上であること
(※)支給開始は60歳から、60歳に達するまでは支給停止
(A男は54歳のため該当しません) - 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害にあり、かつ、婚姻をしていないこと (第1回、2回で登場した子の場合)
ここまでで、A男さんと、C男さんは、遺族厚生年金をもらえないことが確定しました。
しかし、残ったB男さんにも問題があります…
遺族の範囲の中に、「死亡当時、その者によって生計を維持した者」とあります。
年収900万円の人が、65歳年金受給者に生計維持されてた?と、思った方もいらしゃったと思います。そもそも、年額850万円を超えているし…!???
実は、生計を維持していた遺族とは、
死亡当時その者と生計を同じくしていた者であって、厚生労働大臣の定める金額
(年額850万円)以上の収入を将来にわたって得られないとみとめたもののことであり、B男は、5年後定年を迎え、その後850万円以上の収入を得られないと認められれば、
遺族厚生年金を60歳から受給できることになります。
この制度は、
夫(男性)の場合のみ該当し、残された遺族が妻(女性)であれは、年齢については問われません。
このあたりも、男女平等が叫ばれる中、見直しが必要では?との話が出てきています。

さていよいよ次回は、今まで3回を踏まえて、現在遺族年金制度についてどのようなことを検討しようとしているか?を見ていきたいとおもいます。
それでは…








